こんにちは、橋本はじめです。
これまで小学校では、各クラスに1人の担任の先生が1年間を通して子どもたちを見守る「固定担任制」が一般的でした。しかし、最近では「学年担任制」という新しい取り組みを導入する学校が増えてきています。
大阪府羽曳野市立埴生南小学校でも、来年度からこの「学年担任制」を導入することが発表されました。この記事では、学年担任制とはどのような仕組みなのか、またそのメリットやデメリットについて詳しく解説します。
・参考
担任の先生を1カ月交代でローテ 羽曳野の市立小 学年担任制導入へ 大阪府内で初 – 産経ニュース
羽曳野市立埴生(はにふ)南小学校は来年度から、6年生の担任を4人の教員で受け持つ「学年(チーム)担任制」を導入する。従来のように学級の担任を固定せず、1カ月交…
学年担任制とは?
複数の教員で学年全体を担当する仕組み
学年担任制とは、1つの学年を複数の教員で担当する仕組みです。例えば、6年生のクラスが3クラスある場合、4人の教員が交代で担任を務めます。
羽曳野市立埴生南小学校の場合は、1カ月ごとに担任の先生がローテーションし、残りの1人は学年全体のサポートを行う形になるとのことです。
つまり、1年間を通して同じ担任の先生がいるわけではなく、月ごとに先生が入れ替わるため、子どもたちは複数の先生と関わることができます。
なぜ学年担任制を導入するのか?
1. 子どもたちが複数の教員と関われる
従来の固定担任制では、1人の先生が1年間同じクラスを担当するため、子どもたちが相談できる相手は基本的に担任の先生だけでした。
しかし、学年担任制では複数の先生と関わることができるため、子どもたちにとっては「この先生にはこんなことを相談しよう」「この先生は勉強のことをよくわかってくれる」といった選択肢が増えます。
また、先生によって異なる教え方や価値観に触れることができるため、子どもたちの視野を広げるきっかけにもなるでしょう。
2. 教員の負担軽減
これまでの固定担任制では、1人の先生が1年間ずっと同じクラスを担当するため、学級運営や保護者対応、行事の準備など、すべてを担任が一手に引き受けていました。
しかし、学年担任制では複数の先生で分担することができるため、先生の負担も軽減されます。特に、学級のトラブル対応や進路指導など、1人では抱えきれない問題をチームで対応できることは大きなメリットです。
また、1人で学級を1年間受け持つことに不安を感じている先生にとっても、学年全体をサポートし合える体制は心強いものになるでしょう。
学年担任制のメリットとデメリット
メリット
✅ 複数の先生と関わることで相談しやすくなる
✅ さまざまな価値観や考え方に触れられる
✅ 先生同士でサポートし合えるため、教員の負担が軽減される
✅ クラスのトラブルをチームで対応できる
デメリット
❌ 担任の先生が頻繁に変わることで、子どもが戸惑う可能性がある
❌ 先生ごとの対応の違いに混乱する場合がある
❌ 保護者からの連絡窓口が曖昧になる可能性がある
特に「担任の先生が月ごとに入れ替わる」という点は、子どもによっては不安を感じる場合もあるかもしれません。しかし、その分いろいろな先生に相談できる安心感や偏りのない指導が受けられるメリットも大きいと言えます。
学年担任制はこれから広がっていくのか?
学年担任制は、すでに神戸市など一部の地域で導入されており、今後さらに広がる可能性があります。
特に、教員の働き方改革や子どもたちの多様なニーズに応えるためには、このような新しい体制が必要だという声も多くあります。
羽曳野市立埴生南小学校の事例をきっかけに、大阪府内の他の学校でも導入が検討されるかもしれません。
まとめ
学年担任制は、「子どもたちにとっての安心感」と「教員の負担軽減」を両立させるための新しい取り組みです。
最初は「担任の先生が入れ替わるのは不安…」と感じるかもしれませんが、複数の先生と関わることで子どもたちの成長がより豊かになる可能性があります。
これからますます多様化していく教育現場において、学年担任制がどのように定着していくのか、今後の動きにも注目していきたいですね。
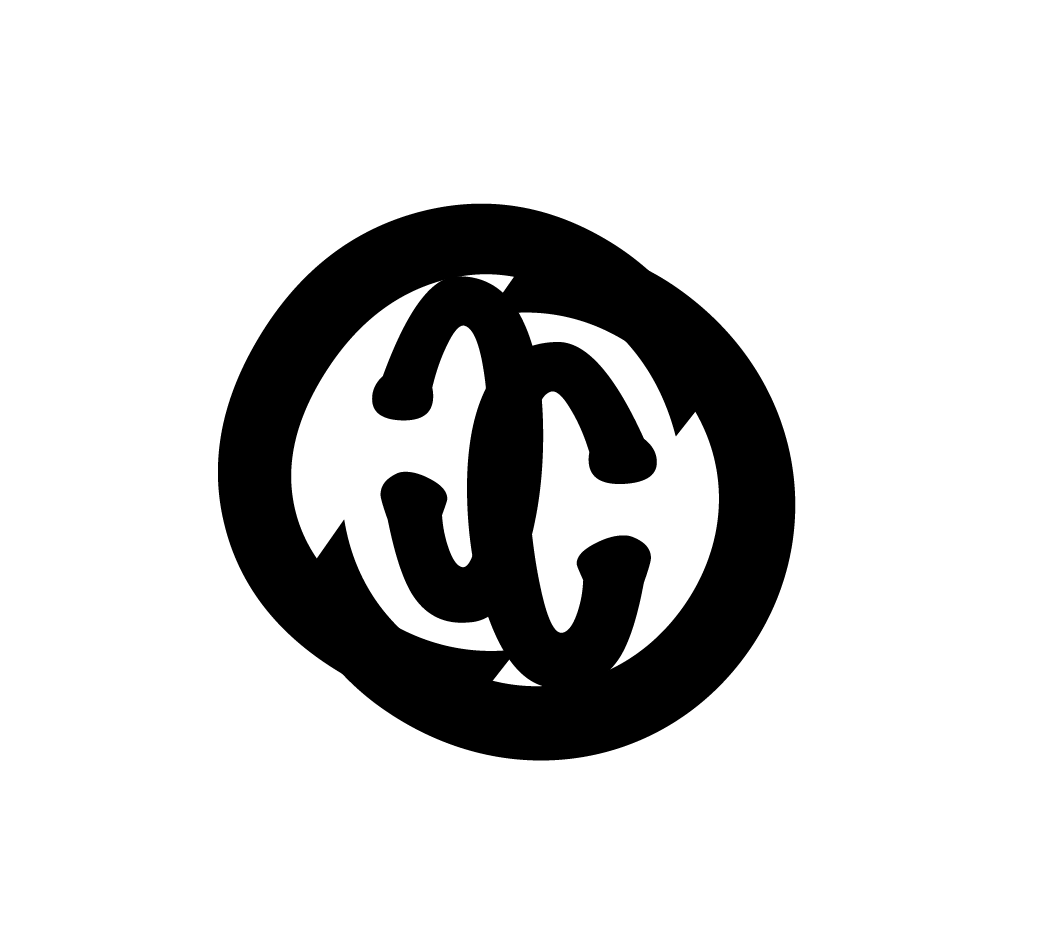
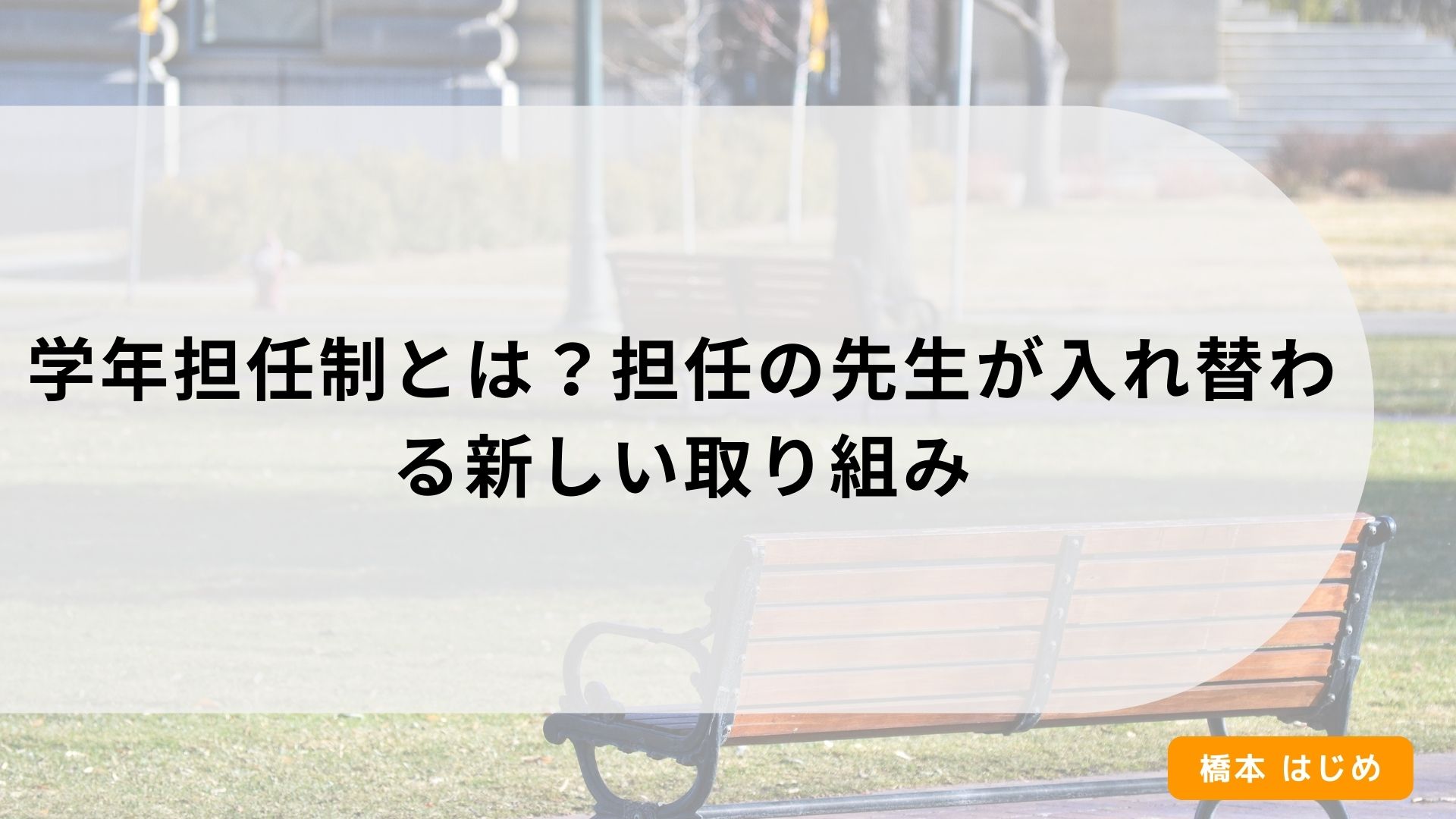

コメントを残す